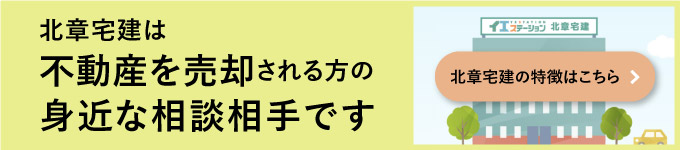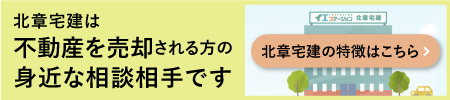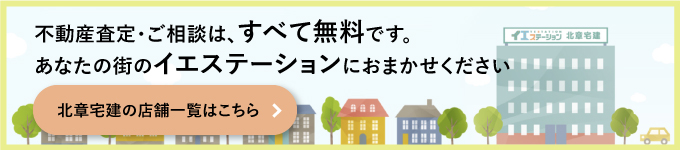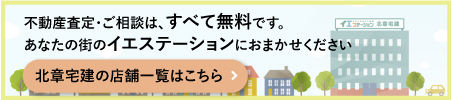土地や空き家のこと2025.07.31
田舎の実家はどうするのが正解?判断軸と選択肢を解説
こんにちは。イエステーション北章宅建 札幌北店の蛸星です。
田舎の実家を相続したものの、遠方で住む予定もなく、どうするべきか迷っているという方も多いのではないでしょうか?
放置していても固定資産税はかかり続けますし、管理の負担も気になりますよね。
今回のコラムでは、田舎の実家を放置するリスクから、売却・活用などの選択肢、判断する際のポイント、手放す場合の注意点まで詳しく解説します。
適切な対処法を見つけるために、ぜひ参考にしてください。

田舎の実家はどうする?放置するとどんなリスクがある?
相続した田舎の実家を前に、「このまま持ち続けて良いのだろうか」「何か対策が必要だろうか」と悩んでいる方は少なくありません。
一つだけはっきりしているのは、何もせず放置するのは避けたほうが良いということです。
実家を長期間そのままにしておくと、下記のようなリスクがあります。
リスク①固定資産税などの金銭的な負担が増える
使っていない家でも、所有している限り固定資産税や都市計画税の支払いは続きます。
さらに、建物が老朽化すれば修繕や管理の費用も発生し、負担が年々増えていくことも珍しくありません。
「住んでいないのに毎年お金だけがかかる」という状況は、想像以上に大きなストレスになります。
リスク②建物の老朽化により、倒壊など周囲に被害を及ぼす
人が住まなくなった家は、驚くほど早く傷み始めます。
定期的な換気や手入れが行われないことで、雨漏りやシロアリ被害が進み、最悪の場合は倒壊する危険性も。
もし建物の一部が崩れて近隣に損害を与えた場合、所有者が損害賠償を求められるケースもあります。
リスク③近隣トラブルの原因になる
空き家を放置すると、草木が伸び放題になったり、害虫や小動物が住み着いたりと、近隣住民に迷惑をかける要因が増えていきます。
不法投棄や不審者の侵入といった治安悪化も心配です。
こうした問題から近所との関係が悪化すれば、後の対処もより難しくなります。
リスク④「特定空家」に指定される可能性
さらに深刻なのは、行政から「特定空家」に指定されるリスクです。
指定されると固定資産税の優遇がなくなってしまいます。
税額が跳ね上がるだけでなく、改善命令に従わなければ強制的に解体され、その費用まで請求されることもあります。
特定空家については、「特定空き家とは?指定されるデメリットや防ぐための対策も紹介」で詳しくお伝えしていますので、ぜひあわせてご覧ください。
田舎の実家は売却?活用?どんな選択肢がある?
田舎の実家の放置は、お金・安全・近隣関係・行政対応の面で大きなリスクを抱えています。
だからこそ、早めに「どうするか」を検討しておくことが重要です。
では、田舎の実家について、どんな選択肢があるのでしょうか?
売却する
田舎の実家を使う予定がなく、できるだけ早く負担をなくしたい人には、売却が最もシンプルな選択肢といえます。
売却すれば管理の手間や固定資産税の支払いが不要になり、まとまった現金も得られます。
相続人の間での分割も、現金ならスムーズに進めやすいでしょう。
ただしデメリットとして、当然のことながら実家を手放すことになりますし、地域によっては買い手が見つかるまで時間がかかる場合もあることに注意が必要です。
賃貸として活用する
田舎の実家を資産として残したい人や、家賃収入を得ながら維持したい人には、賃貸として活用する方法があります。
賃貸に出せば、家賃収入で固定資産税や管理費用をまかなえる可能性があります。
入居者がいれば建物の劣化も防ぎやすく、将来的に自分や家族が使う道を残せるのもメリットです。
ただしデメリットとして、借り手が見つからない空室リスクや、修繕・リフォーム費用の発生、入居者対応など管理の手間が発生することが挙げられます。
セカンドハウス・二拠点居住として活用する
「いつか田舎暮らしをしたい」「週末に自然を楽しみたい」と考えている人には、実家をセカンドハウスや二拠点居住の拠点として活用する方法があります。
活用すれば思い出の家を手放さずに済み、家族や親族が集まる場としても使えます。
リモートワークが普及した今、田舎の家の価値が見直されているのも追い風です。
ただしデメリットとして、定期的に利用しないと劣化が進むことや、維持管理・リフォーム費用がかかる点に注意が必要です。
更地にして土地活用する
建物が老朽化して使い道がない場合は、解体して更地にし、土地として活用する方法もあります。
更地にすることで、老朽化した建物の維持管理が不要になり、駐車場や土地としての活用や売却の幅が広がる可能性も。
ただしデメリットとして、解体費用がかかりますし、固定資産税の優遇(住宅用地の特例)がなくなることで税負担が増す場合もあります。
解体する際の費用や注意点は、「空き家の解体費用はどれくらい?更地にせずに売る方法はある?」で詳しくお伝えしていますので、ぜひあわせてお役立てください。
寄付する
「自分では活用も売却もできない」「社会貢献したい」と考える人には、自治体や法人に寄付する方法もあります。
寄付が受け入れられた場合、固定資産税や管理の負担から完全に解放される点が大きなメリットです。
ただしデメリットとして、寄付を受け入れてくれる先が限られていることが多く、条件や手続きが厳しい場合もあることが挙げられます。
田舎の実家をどうするか迷ったときの判断軸
ここまで紹介した選択肢の中で、どれが自分に合うのか決めかねている方もいるでしょう。
そんなときは、いくつかの視点から田舎の実家の状況や自分の希望を整理してみるのがおすすめです。
将来的に使う予定があるかどうか
まず考えたいのは、実家を将来的に使う可能性があるかどうかです。
自分や家族が住む予定があるのか、セカンドハウスとして活用できるのか、親族に引き継ぐ可能性があるのかなどを確認しましょう。
使い道が明確でなければ、売却など早めの対応を検討するのも一つです。
維持にかかる費用と労力
実家を所有し続ける場合、固定資産税や火災保険、管理費用のほか、遠方なら現地までの交通費や時間も必要です。
これらの負担を長期的に続けられるかどうか、現実的に考えてみることが大切です。
不動産の資産価値と市場状況
地域の不動産相場や将来的な価値を調べることも判断材料になります。
複数の不動産会社に査定を依頼すれば、客観的な市場価値がわかり、売却・活用どちらにするかの目安になります。
家族・相続人の意見
実家の扱いは家族や相続人全員に関わることです。
感情的な問題も生じやすいため、早めに話し合いをして意見を共有し、全員が納得できる方向性を見つけることが重要です。
法的なリスクがあるかどうか
相続登記が済んでいない場合や、共有名義になっている場合は、手続きを進めないと売却や活用ができません。
また、放置による特定空家指定や損害賠償リスクも踏まえ、法的な問題がないかを確認しておきましょう。
田舎の実家を手放す場合の注意点

田舎の実家を売却や寄付で手放す際は、いくつかの重要な注意点があります。
これらを理解しておくことで、トラブルを防ぎ、スムーズな手続きにつながります。
注意点①相続登記はなるべく早く行う
2024年(令和6年)4月から相続登記(被相続人からの名義変更)が義務化されました。
相続を知った日から3年以内に登記の申請を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
売却や寄付を進めるためにも、まず登記が済んでいるか確認しましょう。
相続した不動産が不要な場合の手続きについては、「不動産の相続、いらないときはどうするの?手続きのポイントとは」で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご参考にしてください。
注意点②相続人全員の合意が必要となる
実家を手放す際、実家が共有名義になっている場合や複数の相続人がいる場合、全員の合意がないと手続きを進められません。
後々のトラブルを避けるためにも、早めの話し合いが大切です。
注意点③契約不適合責任を問われる可能性がある
老朽化した建物は不具合が隠れていることがあり、不確かな状況で後から発覚すると、「不具合があるなら買わなかった」などと、売却後に契約不適合責任を問われる可能性があります。
そのため、専門家による調査を受けておくと安心です。
状況によっては、修繕や解体も選択肢になるでしょう。
契約不適合責任について詳しくは「「契約不適合責任」とは何?分かりづらい不動産用語を解説します」でお伝えしています。
注意点④寄付は受け入れの条件が厳しい場合がある
自治体や法人に寄付する場合、受け入れ条件が厳しいことがあります。
手間や期間がかかるため、事前に相談して可否を確認することが重要です。
注意点⑤売却益に税金がかかる場合がある
実家を売却して利益が出ると、譲渡所得税という税金が発生する可能性があります。
つまり、売却は現金が手に入るプラス面だけでなく、税金という金銭的な負担も考慮が必要です。
ただし、相続した空き家を売却する場合は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」など、節税制度を利用できる場合があります。
控除を受けるには一定の条件や手続きが必要なので、事前に税理士や不動産会社に相談しておくと安心です。
譲渡所得税については「不動産売却時の譲渡所得税とは?仕組みや計算方法など詳しく解説」で詳しく解説しています。
まとめ
●田舎の実家を放置すると多くのリスクが生じる
実家の放置は、固定資産税の継続負担、建物の老朽化による倒壊リスク、近隣トラブルなどのリスクがあります。
●選択肢は売却・賃貸・活用・寄付などさまざま
田舎の実家は、売却以外にも、賃貸物件として貸し出す、土地活用するなどの選択肢がありますので、現状に合った方法を選びましょう。
●判断軸を持ち、冷静に検討することが大切
将来の使い道、維持にかかる費用と労力、資産価値、家族の意見、法的な問題など、さまざまな視点から整理することで、自分に合った最適な方法が見えてきます。
●田舎の実家を手放す場合は相続登記義務化に要注意
2024年4月から相続登記が義務化され、相続から3年以内に手続きしないと過料の対象となる可能性があります。
相続人全員の合意や契約不適合責任の確認も忘れずに行いましょう。
北章宅建は、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
空き家に関する相談や無料査定、相続問題など、どんなことでもお気軽にご相談ください。