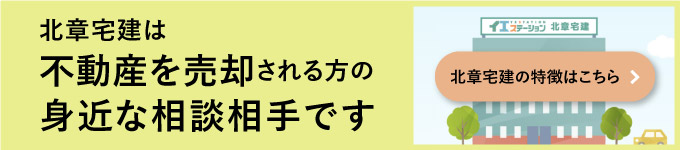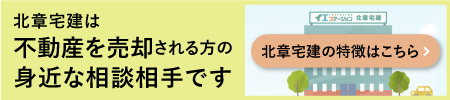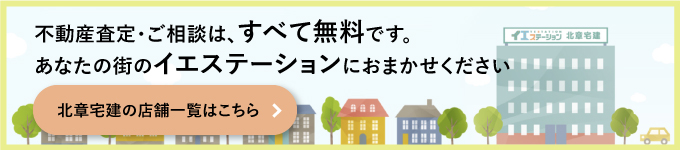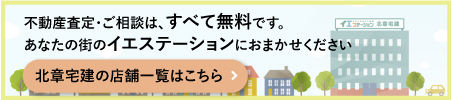不動産管理コラム
不動産管理のこと2025.08.13
賃貸物件の設備交換のタイミングと対応方法を解説
こんにちは。イエステーション北章宅建 不動産管理部の小幡です。
賃貸経営において、設備の交換時期や入居者からの交換要望への対応は、多くのオーナー様が悩まれる問題です。
設備交換は、適切なタイミングで行わないと入居者の満足度低下や、思わぬトラブルにつながることもあります。
今回は、賃貸物件の設備交換のタイミングや入居者からの要望への対応方法、交換時に知っておきたいポイントについて詳しく解説していきます。

賃貸の設備交換のタイミングはいつ?
設備の交換タイミングに迷うオーナー様は多いと思います。
「まだ使えるけど、交換したほうがいいのか?」「壊れてからでも大丈夫なのか?」と悩んでしまうのも無理はありません。
まずは、法的な義務が生じる最低ラインを明確にしておきましょう。
法的に交換が必要になるのは「使えなくなったとき」
民法第606条では「賃貸人は、使用収益に必要な修繕をする義務を負う」とされています。
設備が壊れて、通常の使用ができない状態になれば、オーナー様は修繕または交換の対応をしなければなりません。
つまり、「まだ使えるけど古くて使いにくい」状態での交換は義務ではなく、「壊れて使えない」状態になったときに初めて、法的義務が発生します。
壊れてからでは遅いケースもある
とはいえ、「壊れてから」対応すると、次のようなデメリットもあります。
- 入居者の生活に支障が出る
- 修理・交換の緊急対応で費用が高くなる
- 交換が遅れることで、民法第611条(使用不能時の家賃減額)により家賃収入が減る可能性がある
こうしたリスクを回避するには、設備が完全に故障する前に交換しておくという、計画的な対応が有効です。
設備交換の目安時期(一般的な寿命)
各設備には、一般的に寿命(使用限界や交換の目安時期)とされる年数があります。
- エアコン:約10年
- 給湯器:約10年
- キッチン設備(コンロ・水栓):約10~15年
- トイレ:約10〜15年
- ユニットバス:約15〜20年
もちろん使用状況にもよりますが、これらの年数を過ぎると不具合が増えたり、部品の供給が止まって修理が難しくなったりするケースも出てきます。
メーカーが推奨する「交換時期」を一度確認することをおすすめします。
「故障はしていないけれど、そろそろ交換を検討しても良い時期かも」と判断する際の参考になるでしょう。
もし入居者から設備の交換をお願いされたら?
入居者から「設備を新しいものにしてほしい」「使い勝手が悪いから交換してほしい」といった要望が寄せられることもあります。
こうした要望に対して、オーナー様が対応しなければならないケースと、そうでないケースがあります。
対応が必要なケース(オーナー様に修繕義務が生じる)
民法では、入居者が快適に暮らせるよう、貸主であるオーナー様に「使用収益に必要な修繕義務」があると定められています(第606条)。
以下のような状況では、オーナー様が設備の修理や交換に対応する必要があります。
- エアコンや給湯器などの設備が故障して使えない
- トイレや水回りで水漏れ・排水不良が発生している
- キッチンコンロの点火ができないなど、安全面に支障がある
これらは「故障により通常使用ができない」状態であり、入居者の生活に支障をきたすため、オーナー様の責任で修理や交換を行うことが求められます。
先に触れたように、対応が遅れると家賃の減額請求を受ける可能性もあるため、トラブルを未然に防ぐためにも、早めの対応が大切です。
対応が不要なケース(オーナー様の判断に委ねられる)
一方で、以下のような要望については、必ずしもオーナー様が応じる必要はありません。
- 設備が古く見えるから交換してほしい
- 最新型の機種にしてほしい
- もっと高機能の設備にしてほしい
このようなケースは設備としての機能は十分であり、日常的な使用に支障がない限りオーナー様に対応義務が生じるわけではありません。
ただし、空室対策や入居者の満足度を意識して、設備の更新を積極的に行うオーナー様も増えています。
義務ではなくとも、長期的な経営戦略として検討する価値はあるでしょう。
空室対策として設備交換やリフォームを検討する場合は、「空室対策でリフォームをするときのポイントや注意点を解説」もぜひあわせてご覧ください。
入居者が自ら交換・負担すべきもの
入居者から「設備の一部を交換してほしい」と要望があっても、それが契約上、入居者の負担とされている場合には、オーナー様が対応する必要はありません。
まず確認すべきは、賃貸借契約書や重要事項説明書における記載内容です。
そこに「入居者が交換・管理する消耗品」と明記されているものは、基本的に入居者自身で対応するものと考えられます。
代表的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 電球(LED電球含む)
- エアコンや給湯器のリモコンの電池
- 網戸の張り替え
- ふすまや障子の紙の張り替え
- 水栓のパッキン
- 換気扇のフィルター
入居前に設備や消耗品の扱いについてしっかり説明し、書面で明記しておくことが、トラブルを防ぐポイントです。
賃貸の設備交換に関して知っておきたいこと

設備交換を行う際には、費用面や選び方について押さえておくべきポイントがあります。
交換費用の経費計上について
設備交換にかかった費用は、「修繕費」として経費にできる場合と、「資本的支出」として減価償却が必要な場合があります。
正しく処理することで、節税になるため、基本の考え方を押さえておきましょう。
20万円未満の設備交換 :基本的に「修繕費」で一括経費にできる
修理や交換の費用が1つあたり20万円未満の場合、通常は「修繕費」としてその年の経費にまとめて計上できます(減価償却は不要)。
ただし、古くなった設備を同程度のものに交換する場合は、原状回復や維持管理のためとみなされ、修繕費でOKな場合も。
例えば、古くなったエアコンを同じグレードのものに交換したようなケースでは、20万円以上でも「修繕費」として経費にできる場合があります。
性能が大きくアップする設備交換 :「資本的支出」として減価償却が必要
普通の給湯器を高性能な製品に変更した場合などは、「建物の価値を高めた」と判断され、資本的支出になります。
つまり、その年の経費にはできず、減価償却していく必要があります。
ただし、青色申告をしていれば、30万円未満の設備は「少額減価償却資産」として、たとえ資本的支出であってもその年の経費にまとめて計上できます(年300万円までが上限)。
設備選びの3つのポイント
適切な設備選びは、経営の成功につながります。
設備を選ぶ際は、以下の点を考慮することが重要です。
①費用対効果
最高グレードの設備である必要はなく、物件の家賃帯や入居者層に合わせた一般的なグレードで十分です。
無駄なコストを抑えることで、収益性を確保できるでしょう。
②メンテナンスのしやすさ
故障しにくく、修理実績の多い信頼できるメーカーを選ぶことをおすすめします。
管理コストを抑え、入居者対応の手間を減らせるからです。
③省エネ性能
初期費用は高くても、省エネ性能の高い設備は入居者の光熱費負担を軽減し、物件の競争力向上につながることが期待できます。
経営を成功に導くコツは、「アパート経営でのよくある失敗例。対策と成功を目指すためのポイントも」でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
●賃貸の設備交換は「使えなくなったとき」が最低限のタイミング
法的には「故障して使用できなくなったとき」に交換せず放置すると、契約違反や家賃減額の対象になるおそれがあります。
設備の寿命を目安に、計画的な交換を検討するのがおすすめです。
●入居者から設備交換を求められた場合の対応
故障していない設備については、原則として交換義務はありません。
ただし、入居者の満足度や空室対策の観点から対応を検討するのも一手です。
●設備交換時に知っておきたいポイント
交換費用が20万円未満であれば、一括で修繕費として経費計上が可能です。
設備選びは費用対効果やメンテナンス性、省エネ性能などを考慮し、物件の家賃帯に合った一般的なグレードで十分です。
北章宅建では、都市部以外の賃貸アパート・戸建てを中心に不動産管理を行なっております。
不動産管理のことでお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
著者

小樽駅前店 小幡 将大賃貸物件に関するお悩みや不安、ご相談ごとは、どんなに小さなことでも私たちにお任せください。入居者様にとっては毎日の暮らしを支える住まいであり、オーナー様にとっては大切な資産です。だからこそ、お一人おひとりに寄り添い、誠実で丁寧な対応を心がけています。「ここに相談して良かった」と思っていただけるサービスを、これからも提供してまいります。
この担当者がいる店舗のページ