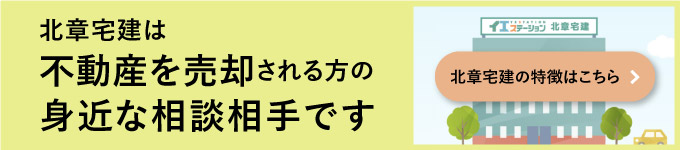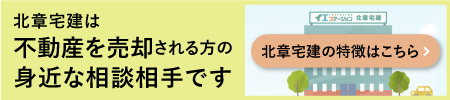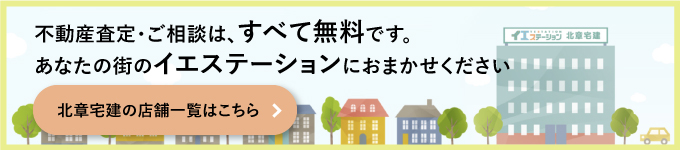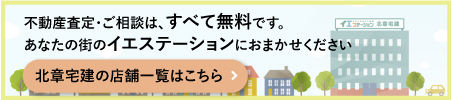不動産管理コラム
不動産管理のこと2025.06.11
アパート経営はペット可が有利?需要とメリット・デメリットを解説
こんにちは。イエステーション北章宅建 不動産管理部の小幡です。
近年、空室対策や収益性向上を目的に、ペット可物件への転換を検討するアパートオーナー様が増えています。
「ペット可にすれば本当に入居率が上がるのだろうか」
「トラブルが心配だが実際のところどうなのか」
そんな疑問をお持ちの方も多いかもしれません。
実際、ペット可物件は適切に運営することで、空室対策として大きな効果を発揮する可能性がありますが、一方でリスクも。
そこで今回は、ペット可物件の需要と供給の現状から、経営上のメリット・デメリット、そして具体的な対策方法まで詳しく解説していきます。

アパート経営で考えたいペット可物件の需要と供給
ペット可物件を検討するにあたり、まず押さえておきたいのは「本当に需要があるのか」「供給は足りているのか」という点です。
ペット可物件の入居ニーズは想像以上
一般社団法人ペットフード協会の「令和6年(2024年)全国犬猫飼育実態調査」によると、2024年時点で、日本国内の犬の飼育世帯数は約514.8万世帯、猫の飼育世帯数は約505.8万世帯にのぼります。
全世帯に対する世帯飼育率は、犬で8.76%、猫で8.61%です。
単純合算では、最大で約1,023万世帯(全世帯の約17.4%)がペット(犬または猫)を飼育している可能性があります。
つまり、日本の約5〜6世帯に1世帯がペット(犬または猫)と暮らしている計算になり、犬・猫以外のペットの種類も考慮すると、アパート経営において「ペット可」の需要は無視できません。
ペット可の物件数はまだまだ少ない
一方で、ペット可物件はまだまだ少数です。
LIFULL HOME’Sが2025年5月に発表した「ペットとの住まい探しの実態調査」によると、住まい探しでペットがいることを理由に不便や困難を感じた人は9割以上にのぼりました。
その背景には、ペット可物件が全体の2割未満にとどまっているという供給不足があります。
このように、高まる入居ニーズと、対応しきれていない供給にギャップがある状況です。
アパート経営において、こうした需給のミスマッチを把握し、「ペット可」を打ち出すことは、空室対策として有効で、差別化にもつながるといえるでしょう。
ペット可の物件の種類とは?
一口に「ペット可」といっても、その内容や対象は物件によってさまざまです。
例えば、以下のような分類が考えられます。
- 小型犬や猫のみ可(中型犬・大型犬は不可)
- 犬はOKだが猫は不可、またはその逆
- 1匹までなど、頭数制限あり
- ペットの種類(爬虫類・鳥類など)に制限あり
- 共有部や移動時にケージ使用必須など、細かい運用ルールあり
このように、ペット可の範囲や条件は物件ごとに異なり、明確な基準づけやルール設定が重要になります。
後のトラブル防止のためには、導入を検討する際、単に「ペット可」にするだけでなく、どのような条件で認めるかを明らかにする必要があるでしょう。
ペット可アパート経営のメリット
ペット可物件への転換は、単なる空室対策にとどまらず、アパート経営にさまざまなメリットをもたらします。
長期入居が期待できる
ペット可物件は依然として少なく、飼育者にとって「今の環境を手放しにくい」という事情があります。
他物件への引越しが難しいため、長期入居につながりやすい点も魅力です。
長く住んでもらえることで、退去時の原状回復や再募集にかかるコストを削減でき、経営の安定化につながります。
専用物件化で入居者間トラブルを未然に防げる
一部の部屋だけをペット可にするのではなく、「全戸ペット可」や「棟ごとの専用化」を行うことで、非飼育者とのトラブルを避けやすくなります。
例えば、ペットの鳴き声や共用部の衛生面をめぐるクレームは、非飼育者との間で起きやすいもの。
最初からペット飼育者のみを入居対象とすることで、価値観の近い入居者同士の安定した環境がつくりやすくなります。
家賃や敷金の設定で収益性を高めやすい
ペット可物件はまだまだ少なく、家賃を1〜2割上乗せしても入居者が見つかるケースが少なくありません。
また、退去時の原状回復に備え、敷金を高めに設定することも可能です。
こうした設定により、通常の賃貸よりも収益性を確保しやすいのが特徴です。
オーナーが有利に交渉を進めやすい
ペット飼育者にとって選択肢は限られているため、「多少高くてもこの物件に住みたい」という心理が働きやすいです。
入居希望者との交渉で家賃の値引き要求が起こりにくく、条件面で譲歩しなくても済むケースが増えるのも、ペット可物件の経営上の強みです。
ペット可アパート経営のデメリットと対策

ペット可物件には多くのメリットがある一方、デメリットや運営上のリスクもあります。
とはいえ、事前に備えておくことで、ほとんどのトラブルは未然に防ぐことが可能です。
デメリット①原状回復費用の増加
ペットによる傷や臭い、毛の付着などで、退去時の清掃や修繕費用が増える可能性があります。
【対策の例】
- 敷金を1〜2カ月分多めに設定
- 退去時の清掃費用を事前に明記(契約書で固定額に)
- ペットによる損耗・汚損は入居者負担とする特約の明文化
これにより、費用面でのリスクをコントロールしやすくなります。
デメリット②近隣住民・入居者間のトラブル
特に「一部の部屋のみペット可」とした場合、鳴き声や共用部の汚れ・臭いがクレームになるリスクがあります。
【対策の例】
- ペット飼育ルールの明文化(頭数・サイズ制限、共用部マナーなど)
- 飼育者限定の住戸設計(棟ごと・階層ごとなどでゾーニング)
- 既存入居者への事前告知と説明
トラブルを未然に防ぐためにも、「誰がどのように飼って良いか」を明確にしておくことが重要です。
また、ペット不可の物件をペット可に変更する場合は、「ペット不可だから入居した」「動物にアレルギーがある」など、既存入居者から反対の声が上がる可能性もあります。
事前に入居者にアンケートを取るなど、ペット可への変更を決める前に対策を行いましょう。
また、中には契約で禁止しているにもかかわらず、入居者が無断でペットを飼育するケースも見られます。
こうした無断飼育への対応方法やリスクについては、「入居者がペットを無断飼育していたら?対応方法や放置するリスク」で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
デメリット③クレーム対応や管理の負担増
ペットが絡むクレームは繊細なものも多く、管理体制が整っていないとオーナー自身の負担が増えてしまいます。
【対策の例】
- ペット可物件の管理経験のある不動産会社に管理を委託
- 定期的な巡回やマナー啓発の実施
- 24時間対応の相談窓口の設置(管理会社連携)
こうした仕組みを整えることで、オーナーが全てを抱え込まずに済む体制がつくれます。
デメリット④一度ペット可にすると、戻しにくい
一度ペット化対応にすると、「試してみたけれど、やっぱりやめたい」となっても、契約変更や既存入居者対応のハードルが高くなります。
【対策の例】
- まずは1部屋〜1棟単位で「試験導入」する
- 募集段階で「○○号室のみ可」「条件付きで可」などと明記
- 市場調査・収支シミュレーションを事前に実施
小規模・段階的な導入で様子を見ながら判断することが、安全な運営につながります。
まとめ
●ペット可物件の需要は高い
現状、日本の全世帯のうち、およそ5〜6世帯に1世帯がペットと暮らしている計算となりますが、ペット可物件は全賃貸物件の2割未満にとどまり、供給が追いついていない状況です。
●ペット可アパート経営のメリット
ペット飼育可能という条件は、入居希望者層の拡大や長期入居の促進になり、経営の安定化につながるでしょう。
また、希少性の高さから家賃や敷金の上乗せがしやすく、交渉の場面でもオーナー側が優位に立ちやすくなります。
●ペット可アパート経営のデメリットと対策
原状回復費用の増加や近隣トラブルなどのリスクはあるものの、事前の契約内容の明確化や管理ルールの整備によって多くは予防・対処が可能です。
無断飼育への備えも含めて、慎重な対応が求められます。
北章宅建では、都市部以外の賃貸アパート・戸建てを中心に不動産管理を行なっております。
不動産管理のことでお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
著者

小樽駅前店 小幡 将大賃貸物件に関するお悩みや不安、ご相談ごとは、どんなに小さなことでも私たちにお任せください。入居者様にとっては毎日の暮らしを支える住まいであり、オーナー様にとっては大切な資産です。だからこそ、お一人おひとりに寄り添い、誠実で丁寧な対応を心がけています。「ここに相談して良かった」と思っていただけるサービスを、これからも提供してまいります。
この担当者がいる店舗のページ