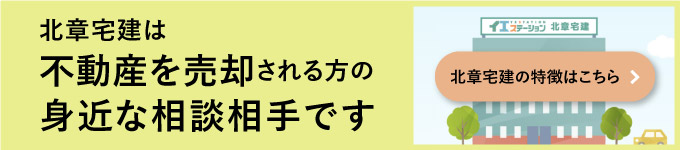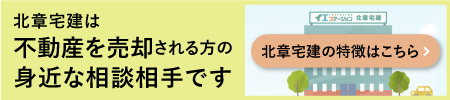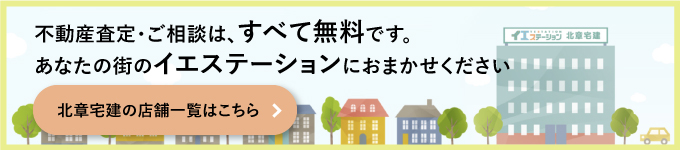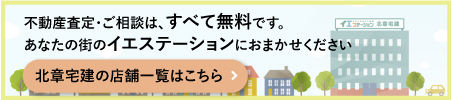不動産管理コラム
不動産管理のこと2025.06.25
賃貸アパートが水漏れ?大家の責任範囲と対応方法を解説
こんにちは。イエステーション北章宅建 不動産管理部の小幡です。
賃貸アパート経営において、水漏れトラブルは避けて通れない問題の一つです。
「水漏れが発生したとき、どこまで大家が責任を負うのだろうか」「修繕費用は誰が負担するべきなのか」と不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
水漏れトラブルは放置すると被害が拡大し、入居者との信頼関係にも影響を与えてしまう可能性があります。
トラブルを最小限に抑えるには、適切な対応が重要です。
今回は、賃貸物件における水漏れトラブルに対する大家の責任範囲と、適切な対応方法について詳しく解説していきます。

賃貸物件の水漏れに対する大家の責任と判断基準
「水漏れが起きたら、大家である自分が責任を負うのだろうか?」
そんな疑問を持つオーナー様は多いのではないでしょうか。
ここでは、法律上の修繕義務を踏まえた責任の判断基準と、原因別の負担区分などについて解説します。
大家に課される「修繕義務」とは
前提として、民法第606条では「賃貸人は、賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負う」と定められています。
ただし、全ての水漏れに対して大家が責任を負うわけではありません。
水漏れの「原因」がどこにあるのかによって、責任の所在が変わります。
水漏れの原因別にみる責任の所在
水漏れの代表的な原因と、それぞれの責任の所在は以下の通りです。
- 設備不良や老朽化による水漏れ → 大家の責任
- 入居者の過失による水漏れ → 入居者の責任
- 自然災害など不可抗力による水漏れ → 修繕は大家の責任だが、賠償は原則なし
大家の責任となるケース
- 給排水管の経年劣化や破損
- 外壁や屋上の防水不良
- 浴室のパッキンやエアコンのドレンホースの劣化 など
特に、「壊れそうな兆候があったのに放置していた」と判断されると、入居者の家財や生活用品への被害についても賠償責任が生じる可能性があります。
また、台風や豪雨、地震などの自然災害が原因で水漏れが発生した場合は、修繕義務は大家にあります。
一方で、大家に過失がない限り、入居者が住めなくなったことに対する損害賠償までは求められないのが一般的です。
ただし、修繕を怠った場合や対応に問題があった場合は、責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。
大家の責任ではないケース
- 風呂の水の止め忘れ
- 洗濯機ホースの外れ
- 排水溝の掃除不足による詰まり
- 寒冷地での水抜き忘れによる凍結 など
入居者の不注意や使い方の問題で水漏れが起きた場合は、修繕費や階下の被害に対する賠償は入居者の負担となります。
これは、民法第606条のただし書きにより、「借主(入居者)の責任によって修繕が必要になった場合、賃貸人(大家)は修繕義務を負わない」と定められているためです。
修繕や賠償にかかる費用の目安
水漏れの被害が軽微な場合は、比較的低コストでの対応が可能ですが、被害が広がると数十万〜数百万円単位の出費になることもあります。
修繕や賠償にかかる費用は以下のような内容を含みます。
- 内装修理費(壁紙やフローリングの張替えなど)
- 家財のクリーニング費・時価賠償(衣類や家具、家電など)
- 仮住まいの費用(必要に応じて、ホテル等の宿泊費補償)
火災保険の適用範囲や補償上限額についても、あらかじめ契約内容を確認しておくと安心です。
賃貸物件の水漏れトラブルを防ぐ賃貸管理のポイント
水漏れトラブルは、一度起きてしまうと修繕や賠償に多くの時間と費用がかかります。
だからこそ、大家としては「水漏れの発生そのものを防ぐ」「発生後のトラブルに発展させない」という両面の予防管理が重要です。
ここでは、実践しやすく効果的な対策を4つご紹介します。
対策①定期的な設備点検を行う
水漏れの多くは、配管や排水設備の劣化・詰まりなどが原因で発生しています。
築年数が経過した物件では、事前の点検と簡単なメンテナンスでリスクを大幅に減らすことが可能です。
点検のポイントは以下の通りです。
- 給水・排水管の劣化確認(サビ・にじみ・接続部の緩み)
- エアコンや洗濯機のドレンホースの詰まり確認
- キッチン・洗面所・浴室などの排水口清掃
目安としては年1〜2回程度の定期点検を行い、異常があれば早めに対応することが大切です。
簡単な清掃・交換で済むことも多く、長期的にはコスト削減にもつながります。
対策②水回りの設備を更新する
特に築年数の古い物件では、設備自体を更新することで水漏れのリスクを軽減できる場合があります。
例えば、自動給湯停止機能つきの風呂の導入や、防水パン(洗濯機用トレイ)の設置です。
設備更新により、「水の止め忘れ」や「排水ホースの外れ」などによる水漏れ被害を軽減できます。
対策③管理会社の活用で体制を整える
大家自身で設備管理を行うのが難しい場合は、管理会社に一部または全体を委託することも有効です。
設備の老朽化状況を踏まえた中長期的な修繕計画も立てやすくなるため、突発的な水漏れにも冷静に対処できる体制が整うでしょう。
対策④契約書でトラブル時の対応を明らかにする
水漏れが発生した後のトラブルを防ぐ備えをしておくことが大切です。
中でも、契約書に「大家と入居者の役割」を明記しておくことは、誤解や責任の押し付け合いを防ぐ重要な対策になります。
責任の所在が不明確なままだと、対応が遅くなりトラブルに発展しやすくなります。
例えば、以下のような文言を盛り込むと良いでしょう。
- 緊急時には貸主または管理者が室内に立ち入る場合がある
- 調査・修繕の必要がある場合は、借主は協力すること
- 異常を発見した際は速やかに貸主へ報告すること
- 借主の不注意により発生した水漏れについては、借主が損害を賠償する責任を負う
こうした項目を事前に明記し、契約時に丁寧に説明しておけば、万が一の際もトラブルに発展しづらいです。
賃貸物件で水漏れが起きた場合の対応手順

水漏れは突然起きるトラブルですが、慌てず適切に対処することで、被害の拡大や入居者とのトラブルを防げます。
水漏れが起きた際に大家が取るべき対応について、順を追って解説します。
ステップ① 入居者からの連絡内容を確認する
まずは、入居者からの連絡内容を正確に把握しましょう。
- どこから水漏れしているか(天井・壁・床・設備など)
- いつ頃から発生しているか
- 水漏れの状態(ぽたぽた、水たまり、浸水など)
- 被害の範囲(入居者宅のみか、他室・階下にも及んでいるか)
緊急性の有無を判断し、必要な対応の優先順位を整理します。
ステップ② 緊急時は応急処置と業者手配を急ぐ
「漏水が止まらない」「階下に影響が出ている」など緊急性が高い場合は、すぐに対応が必要です。
まず入居者に止水栓の位置を伝え、応急的に止水してもらいましょう。
その後、緊急対応が可能な修理業者に速やかに連絡・出動依頼を行います。
階下など他室に影響がある場合は、該当入居者へも早急に連絡しましょう。
ステップ③ 現場の確認と記録を行う
できるだけ早く現地に赴き、状況を確認・記録します。
確認・記録をすべき事項は以下の通りです。
- 水漏れ箇所の写真や動画撮影
- 濡れた家財や被害範囲の記録
- 状況のメモ(日時・天候・聞き取り内容など)
記録は、保険申請・賠償交渉・原因特定などに不可欠です。
原因が不明な段階では責任を断定せず、中立的な立場で進めましょう。
ステップ④ 専門業者・保険会社へ連絡する
原因調査と修理を進めるにあたり、まず
水道業者や設備業者への修理依頼を行います。
大家側に責任がある可能性がある場合は火災保険会社へ事故報告、入居者側の過失が疑われる場合は、火災保険や個人賠償責任保険の確認を促しましょう。
ステップ⑤ 入居者への説明とフォローを丁寧に行う
原因調査が進んだ段階で、入居者や被害を受けた他の居住者へ、次のような内容を丁寧に説明しましょう。
- 何が原因で水漏れが起きたか
- 今後どのように対応を進めるか
- 誰がどこまで責任を負うのか(保険対応の可否を含む)
修繕により入居者の生活に支障が出る場合は、仮住まいや代替対応、見舞金なども視野に入れます。
対応が長引くときは、こまめな連絡や丁寧な説明を心がけ、信頼関係の維持に努めましょう。
入居者対応については、「賃貸管理のクレームの事例と適切な対応について解説」もぜひご参照ください。
感情的な対立を避け、スムーズに解決へ導くためのヒントをご紹介しています。
まとめ
●水漏れが起きたらまずは原因を明確に
水漏れの原因によって、大家が責任を負うかどうかは異なります。
老朽化や設備不良によるものは大家の負担となり、入居者の過失によるものは入居者が修繕・賠償義務を負うのが原則です。
●賃貸物件の水漏れトラブルを防ぐポイント
水漏れトラブルを未然に防ぐには、定期点検の実施と、契約書による役割や対応ルールの明文化が重要です。
●賃貸物件で水漏れが起きた場合は速やかに対応しよう
水漏れ発生時は、速やかな現場確認と被害状況の記録が第一です。
専門業者や保険会社と連携しながら原因調査を進め、入居者への丁寧な説明と誠意あるフォローを心がけることで、トラブルの拡大を防ぎやすくなります。
北章宅建では、都市部以外の賃貸アパート・戸建てを中心に不動産管理を行なっております。
不動産管理のことでお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
著者

小樽駅前店 小幡 将大賃貸物件に関するお悩みや不安、ご相談ごとは、どんなに小さなことでも私たちにお任せください。入居者様にとっては毎日の暮らしを支える住まいであり、オーナー様にとっては大切な資産です。だからこそ、お一人おひとりに寄り添い、誠実で丁寧な対応を心がけています。「ここに相談して良かった」と思っていただけるサービスを、これからも提供してまいります。
この担当者がいる店舗のページ