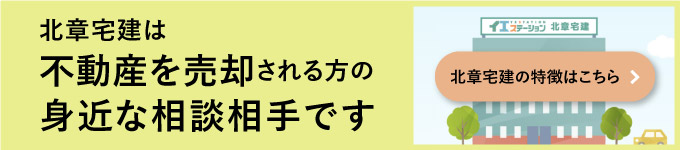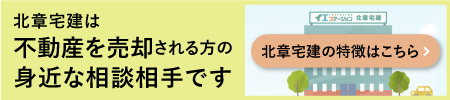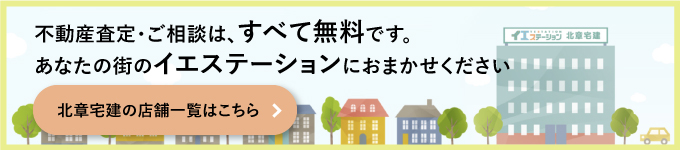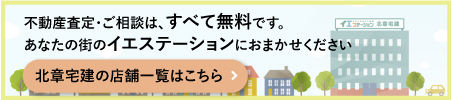不動産売却のコツ2025.03.02
不動産売却での土地・建物の按分を解説。どのような方法がある?
こんにちは。イエステーション北章宅建 滝川店の上家です。
不動産売却を考えている方の中には、「土地と建物の按分」という言葉に初めて触れる方も多いのではないでしょうか。
不動産の売却価格は総額として表示されることが多いため、土地と建物を分けて考える必要性を感じない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、税金の計算や契約書の作成において、この按分が重要な役割を果たします。
今回は、不動産売却時の土地・建物の按分について詳しく解説していきます。

不動産売却時の土地・建物の「按分」とは?
「按分(あんぶん)」とは、一言で言うと「分ける」という意味です。
不動産売却における按分とは、土地と建物が一体となった不動産の価格を、「土地部分」と「建物部分」に分けて計算することを指します。
例えば、不動産を4,000万円で売却する場合、土地が2,500万円、建物が1,500万円というように内訳を明確にすることです。
多くの不動産広告では土地と建物の合計額のみが表示されており、それぞれの内訳は明記されていないことが一般的です。
では、なぜ按分を行う必要があるのでしょうか?
按分を行う主な理由は下記の2つです。
理由1|土地と建物では消費税の扱いが異なるから
1つ目の理由は、土地と建物では消費税の扱いが異なるからです。
土地は消費税が非課税ですが、建物には消費税がかかります。
これは、土地は時間が経っても劣化しないとみなされる一方、建物は経年劣化する消費財とみなされるためです。
事業用不動産を売却する場合や売り主が課税事業者の場合、建物にかかる消費税を納税する義務があるため、正確な消費税額を算出するには按分が必要になります。
家の売却時の消費税についての詳しい内容は、「家の売却の際の消費税の課税と非課税の対象とは?」というコラムで詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
理由2|減価償却費の計算のため
2つ目に、減価償却費を計算するためという理由もあります。
減価償却とは、建物など時間の経過とともに価値が減少する資産について、その価値の減少分を費用として計上する会計上の処理です。
「土地は価値が減少しない」と考えられるため減価償却の対象になりませんが、建物は対象となります。
そのため、建物の価格を正確に把握するためにも、土地の金額と分けて考える必要があるのです。
不動産売却時の土地・建物の按分方法
土地と建物の按分方法には、主に下記の4つの方法が挙げられます。
- 固定資産税評価額による按分方法
- 不動産鑑定士による鑑定評価額を採用する方法
- 建物(または土地)の時価を優先的に計算する方法
- それぞれの時価により按分する方法
それぞれの方法について見ていきましょう。
固定資産税評価額による按分方法
固定資産税評価額を基準にした按分方法は、最も一般的で客観的な方法の一つです。
この方法は、市区町村が定めた公的な評価額を使用するので、私的な利害が入りにくく、トラブルになりにくい評価基準といえます。
【計算手順】
1.土地と建物それぞれの固定資産税評価額の比率を求める
2.求めた比率を売買価格に適用する
3.求めた比率で土地と建物の金額を按分する
計算例として、「不動産売却価格が4,500万円(税込)、土地の固定資産税評価額が1,800万円、建物の固定資産税評価額が1,200万円の場合」を考えてみましょう。
1.建物の割合を計算
建物の固定資産税評価額 ÷(土地と建物の固定資産税評価額の合計)
1,200万円 ÷ 3,000万円 = 40%
2.土地の割合を計算
100% − 40% = 60%
3.消費税を考慮した建物割合を計算(消費税率10%の場合)
建物割合 ×(1 + 消費税率)
40% × 1.1 = 44%
4.土地と建物それぞれの金額を算出
- 土地の金額:4,500万円 × 60% = 約2,700万円
- 建物の金額(税抜):4,500万円 × (40% ÷ 1.1) ≈ 約1,636万円
- 建物の金額(税込):4,500万円 × 44% ≈ 約1,980万円
例えば、土地の評価額が建物の評価額の2倍であれば、売買価格も同じ比率で按分します。
誰でも確認できる公的な数値を使うため、按分の根拠を説明しやすいメリットがあります。
国税庁もホームページで推奨しており、客観的な数値に基づくため、売り主と買い主の双方が納得しやすい方法です。
不動産鑑定士による鑑定評価額を採用する方法
より正確に按分するためには、不動産鑑定士に依頼して評価額を出してもらう方法も選択肢の一つです。
【計算手順】
1.不動産鑑定士に土地と建物の評価を依頼する
2.鑑定結果に基づいて土地と建物の価値の比率を決定する
3.決定された比率で売買価格を按分する
不動産鑑定士は国家資格を持つ専門家で、国の基準をもとに不動産の価値を評価します。
客観性が高く、税務署などからも信頼されるため、安心感があります。
費用はかかりますが、後々のトラブル防止に役立ちます。
特に高額な不動産や特殊な条件がある物件に適した方法です。
建物(または土地)の時価を優先的に計算する方法
建物あるいは土地の時価を先に計算し、売買価格からその金額を差し引いて、もう一方の価格を算出する方法も選択肢の一つです。
【計算手順】
1.建物または土地のどちらかの時価を先に計算する
2.売買価格からその計算した時価を差し引く
3.残りの金額をもう一方(土地または建物)の価格とする
計算が比較的簡単で、迅速に按分できるメリットがあります。
建物の価値は、国が公表している「建物の標準的な建築価額表」などを参考にすることができますよ。
ただし、優先させた時価と実際の売買価格に大きな差がある場合は、適切ではない可能性があることに注意しましょう。
それぞれの時価により按分する方法
土地と建物それぞれの時価を求め、その割合で売却金額を按分する方法も有効な選択肢です。
【計算手順】
1.土地と建物の時価をそれぞれ算出する
2.算出した時価の比率を求める
3.その比率に基づいて売買価格を按分する
例えば、土地は「路線価」などを参考にして時価を算出し、建物は建築費や経年劣化などを考慮して時価を算出します。
この方法は、土地と建物の両方をきちんと評価するため、より公平な按分が可能になります。
ただし、時価の算出方法によって結果が変わることがあるので、信頼できる情報源を使用することが大切です。
不動産売却における土地・建物の按分は公平な方法の選択をしよう

土地と建物の按分を行う際には、売り主と買い主のどちらか一方が極端に有利にならないように注意する必要があります。
なぜなら、按分比率によって両者の税負担に大きな影響が出るからです。
両者の負担の違いを説明しましょう。
売り主と買い主では立場の違いにより按分の希望が異なる
土地と建物の按分では、下記のように、売り主と買い主では望ましい比率が真逆になるという大きな違いがあります。
- 売り主の場合:建物の割合を低くしたい(土地の割合を高くしたい)
- 買い主の場合:建物の割合を高くしたい(土地の割合を低くしたい)
事業用不動産を売却する場合や課税事業者が不動産を売却する場合、売り主としては、建物部分に消費税がかかるため、建物割合が低いほど納税額が少なくなりますし、手取り額を最大化したい場合は土地の比率を高くするほうが有利となります。
一方、買い主側が建物を事業用資産として購入した場合、建物部分の消費税は仕入税額控除の対象となります。
消費税課税事業者であれば、建物の割合が高いほど消費税の支払額を減らすことができ、場合によっては還付を受けることが可能です。
ただし、事業用資産として使用することが前提です。
また、建物は減価償却の対象となるため、建物価格が高いほど経費計上できる金額が増え、事業者でない個人でも長期的に税負担を軽減できる可能性があります。
このように両者の利害は対立するため、極端に按分が偏るとトラブルの原因になりやすいのです。
公平な按分方法の選択をしよう
上記のように負担の違いがあることから、按分方法を選ぶ際は、売り主と買い主の双方が納得できる客観的かつ合理的な方法を選ぶことが大切です。
固定資産税評価額を基準にした按分方法は、公的な基準を用いるため公平性が高いといえます。
客観的なデータに基づく方法であれば、後々トラブルになるリスクも低減できます。
また、極端に偏った按分は税務署から否認されるリスクもあります。
極端な比率設定は避け、合理的な根拠に基づいた按分を心がけましょう。
なお、按分には税金の計算が伴います。
不動産売却では按分以外にもさまざまな税金が発生するため、事前に把握することが大切です。
いつどのような税金を支払う必要があるのか知っておくことで、スムーズな売却手続きが可能になるでしょう。
不動産売却に関連する税金の支払いタイミングなどについては、「不動産売却の税金はいつ払う?種類や支払いのタイミングを解説」で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
まとめ
●不動産売却での土地・建物の「按分」とは価格の内訳を決めること
不動産売却における按分とは、土地と建物が一体となった不動産の価格を、土地部分と建物部分に分けて計算することです。
●按分方法には固定資産税評価額による方法など複数の選択肢がある
按分方法には、固定資産税評価額を利用する方法や不動産鑑定士による評価額を採用する方法など、いくつかの選択肢があります。
それぞれの方法によって計算結果が異なるため、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
●按分は売り主・買い主双方にとって公平な方法で行うべき
按分比率は売り主と買い主の税負担に大きな影響を与えるため、極端に偏った按分はトラブルの原因になります。
客観的かつ合理的な方法で按分を行い、双方が納得できる結果を目指しましょう。
北章宅建は、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
空き家に関する相談や無料査定、相続問題など、どんなことでもお気軽にご相談ください。
著者

滝川店 上家 郁也現在は中空知、北空知、留萌地方を担当しております。過去には賃貸仲介業務にも携わってきました。 ご相談の際は売却・購入とともに賃貸との比較など、経験を活かしたご提案をさせていただきます。 私自身の個人的な経験では、中古住宅を購入してリフォームを行っておりますし、親族の不動産取引の委任を受け、売却の手伝いも経験致しました。それらの経験からもお客様にアドバイスできると思います。不動産のことでお困りでしたら、ぜひお任せください。
この担当者がいる店舗のページ